関連用語集

納骨
納骨とは遺骨をお墓に収めることです。近年は納骨堂などお墓以外への納骨も増えています。

改葬
お墓に埋葬されている遺体、遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことをいいます。なお、改葬の手続きは、墓地・埋葬等に関する法律により定められています。

合祀墓
複数の遺骨をまとめて合葬するお墓のことです。骨壷から遺骨を出し直接お墓へ納骨しますので、合葬墓、合同墓とも呼ばれるます。

散骨
遺骨を粉状の粉骨にし、海や山などに撒く自然葬のこと。海に撒く場合は海洋散骨と言い、2ミリ以下の粉骨状にすることが望ましいとされている。

手元供養
遺骨をお墓に納めないで自宅の仏壇などで保管し供養を行うこと。

墓じまい
墓石を撤去し、その場所を更地にして、使用していた権利を返還すること。中にある遺骨は取り出し、別の場所へ移します。勝手には出来ないので、手続きが必要です。

永代供養
墓地や霊園を管理している宗教法人がある一定の期間(一般的には33回忌まで)を決めその間供養を行うこと。その後は合祀される。近年は永代供養と言っても様々な形があります。

納骨堂
遺骨を屋内で保管する場所のこと。お参り時の天候に左右されず、またお墓掃除も必要ないことで普及。

埋葬
遺体や遺骨をお墓へに納めること、土葬の場合、遺体をお墓へ埋めることを、火葬の場合はお墓や納骨堂などへ遺骨を納めることを言う。墓地、埋葬等に関する法律からきている。

埋蔵
埋蔵とは埋め隠すという意味で、土葬の場合にイメージしやすいかもしれません。近年は土に埋めることはほとんどありませんが、公営霊園などでこの埋蔵という言葉が使われています。

収蔵
収蔵とは、物を取り入れてしまっておくことで、納骨堂に骨壷ごと納める時にこの言葉が使われています。

大施餓鬼会
毎年行われるお寺の年間行事の1つで地獄にいる餓鬼(悪行により地獄に落ちた魂や霊)に施しを行いこの世にいる私達の極楽往生を願う法要のことで、曹洞宗では施餓鬼ではなく施食会という。多くの僧侶と檀家が集まり行われる。

檀家
「ダーナパティ」というサンスクリット語が由来で、特定の寺院を経済的に支える家のこと、葬祭供養をその寺に任せる代わりに布施として経済支援を行う。江戸時代に制度化され現在に至る。

卒塔婆
法要の時に先祖や故人を供養するための細長い板のことで、追善供養を行う時に用いるもので、塔婆(卒塔婆)を立てることは善を積むことに繋がります。サンスクリット語の「ストゥーパ」が由来。

葬送
故人の遺体を葬るために墓所まで送ること、またはその儀式で、野辺送りともいう。

直葬
お通夜や告別式をせず直接火葬場で火葬式のみを行う葬送方法のことで、近年増加傾向です。

共同墓��地
集落や地域で管理・使用している墓地と、通常の家墓より大きい1つのお墓に複数の遺骨を納骨する墓地の2つが該当しますが、ここでは後者の複数の遺骨を納骨するお墓のことです。

永代供養墓
一定期間(寺院や契約により異なる)の永代供養権がついた墓地のことで、身内にお墓を見る人がいなくても墓地管理者(宗教法人)が一定期間の管理、供養を行ってもらえるお墓のことです。

受入証明書
改葬の際、引越し先の管理者が遺骨の受入を承認したことを証明するための書類

墓地使用許可証
墓地使用許可証とは、その墓地を使用する権利を示す書類で、墓地使用承諾書や永代使用承諾証などとも呼ばれます。
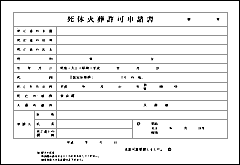
埋葬許可証
市区町村から発行された火葬許可証は火葬後に火葬場で押印されたものが埋葬許可証となります。墓地など埋葬時に必要となります。

改葬許可証
改葬などによりお墓を移転する場合には必要となる書類のことで、移転元の各自治体に申請すると改葬許可証を発行してもらえます。

昇天者記念礼拝
キリスト教で毎年行われている法要のことで、多くの信者が参加し行われる教会の行事。

閉眼供養
閉眼法要や御魂抜きとも言われ、お墓や位牌に宿った仏様の魂を鎮め抜き取る供養のことをいいます。

開眼供養
開眼法要や御魂入れとも言い、お墓や位牌に故人の魂が宿ったものに変えてもらう供養のことを言います。

極楽浄土
浄土宗や浄土真宗では阿弥陀仏の浄土のことを極楽浄土といいます。浄土とは清浄な国土を意味し、それに対して人間の住んでいる世界は娑婆、穢土などと言われます。

キリスト教
キリスト教とはナザレのイエスをキリストとして信じる宗教でイエス・キリストが神の国の福音を説き罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ復活したものと信じられている。現在教派は14あり、初代教会、西方教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、ルーテル教会、改革派教会、会衆派教会、メソジスト教会、パプテスト教会、アナパプテスト教会、東方正教会、正教会、東方諸教会があり父なる神とその子キリストと聖霊を唯一の神(三位一体)として信仰する世界最大の宗教です。

イスラム教
イスラム教は、唯一絶対の神を信仰し神が最後の預言者を通じて人々に下したとされるクルアーンの教えを信じ従う一神教です。漢字圏では回教とも呼ばれる。偶像崇拝を徹底的に排除し神への崇拝を重んじ信徒同士の相互扶助関係や一体感を重んじる点に大きな特徴がある。聖地はメッカ。世界第2位の信者を誇る宗教です。

ヒンドゥー教
ヒンドゥー教はインドやネパールで多数派を占める他民族宗教またはインド的伝統を示します。世界で3番めに信者の多い宗教です。ヒンドゥーとはサンスクリット語でインダス川を意味し、西欧に渡りインドに逆輸入され定着しました。神々への信仰と同時に輪廻や解脱など独特の概念をもち、ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァの三神一体とされている。

仏教
世界三大宗教の一つで、信者数は4番目に多い宗教です。インドの釈迦が悟りを開いて仏陀となり、開祖とする宗教で、苦の輪廻から解脱することを目指しているとさせる。年月と共に形を変えながら東南アジアでは上座部仏教が、チベットでは密教、そして東アジアでは大乗仏教が広まった。日本では多くの宗派が誕生し現在に至る。

ユダヤ教
ユダヤ教は古代の中近東で始まった唯一神ヤハウェを神とし選民思想やメシアなどを特色とするユダヤ人の民衆宗教でタナハが重要な聖典とされています。現代では多数の教派があります。

シーク教
シーク教は16世紀にグル・ナーナクがインドで始めた宗教で、サンスクリット語でシシュヤに由来する言葉で弟子を意味する。本部はインドのパンジャーブ州にあります。

ゾロアスター教
ゾロアスター教は古代ペルシアを起源とする善悪二元論的な宗教です。世界最古の一神教です。

ジャイナ教
ジャイナ教はマハーヴィーラを祖師と仰ぎ、特に不害の禁戒を厳守するなど徹底した苦行・禁欲主義をもって知られるインドの宗教でジナ教とも呼ばれる。

道教
道教は中国三大宗教の1つで漢民族の伝統的な宗教。中心概念の道(タオ)は宇宙と人生の根源的な不滅の真理を示している。この道と一体となる修行のため錬丹術を用いて不老不死の霊薬、丹を練り仙人になることを究極の理想とする。

火葬
火葬は葬送方法の1手段で、遺体を焼却すること。または葬儀全体を指すことにも使われる。日本では縄文時代の遺跡からも出土している。

土葬
土葬とは、遺体をそのまま埋葬すること。最も古いのはネアンデルタール人のものが知られている。

風葬
風葬とは遺体を埋葬せずに外気に晒して自然に還す葬送のこと。遺体の腐敗が速い低緯度地域で多く見られ、日本ではその昔、沖縄や奄美地方で一般的に行われていたようです。

水葬
水葬とは海や川に沈める葬送の方法。ヒンドゥー教は宗教の一環としてガンジス川へ水葬しています。また戦争での犠牲者や洋上での死者なども水葬されることがあります。

鳥葬
鳥葬はチベット仏教では一般的な葬送方法で、インドのゾロアスター教でも行われている。遺体をハゲワシなどに与えること。

エンバーミング
エンバーミングとは遺体を消毒、保存処理または修復することで長期保存をかのうにする技法。アメリカやカナダでは遺体のエンバーミングは一般的に行われる。

ミサ
カトリック教会での聖体の秘跡が行われる典礼のこと。キリスト教などの祭礼をミサと呼んでいることがあるが、正式にはカトリック教会のみで、プロテスタントはエウカリスト(聖餐式)、正教会では聖体礼儀という。

賛美歌
賛美歌とはキリスト教(特にプロテスタント)において礼拝や集会で歌われる神を称える歌のこと。

献花
献花とはキリスト教での、亡くなった方へ花を献げることで、仏式での焼香にあたりますが、厳密な解釈としては、棺を飾って送り出す気持ちとか、弔問者の気持ちを表す方法としてお花を送ります。

コリヴァ・ブリヌイ
コリヴァやブリヌイはロシアの葬儀やお祝い事の時に出される伝統料理。コリヴァは小麦に蜂蜜やレーズン、ナッツなどを入れて煮たお粥のようなもの。ブリヌイは直径13センチ~18センチの薄いクレープまたはパンケーキのこと。

イマーム
イマームとはイスラム教の指導者のこと。スンナ派では大小の宗教団体を指導する統率者のこといい、シーア派では宗教団体の最高指導者のことをいう。

メッカ
メッカはサウジアラビアのマッカ州の州都で、正式名はマッカ・アル。イスラム教最大の聖地で、祈りを捧げるところ。

カファン
カファンとは、イスラム教で洗礼した遺体全体を包む白い真新しい綿の布(経衣)のこと。

ムッラー
ムッラーとはイスラム教の法や教義に深く精通した人のことで、モスクでは祈りを導き説教を提供し、出生儀礼や葬儀を行う人。

カオダイ教
カオダイ教は1919年に唱えられたベトナムの新宗教のことで、五教(儒教・道教・キリスト教・仏教・イスラム教)の教えを土台としたことでカオダイ(高台)と名付けられた。

ホアハオ教
ホアハオ教はベトナムのメコン川に面する安江省で1939年に設立した仏教系新宗教で、僧侶や寺院を置かず紫色の布を信仰の対象とするのが特徴です。

コーラン
コーラン(クルアーン)とはアラビア語で書かれたイスラム教の根本聖典です。イスラムの信仰では唯一無二の神から最後の預言者に任命されたムハンマドに対して下された啓示と位置づけられています。

祭祀承継者
祭祀承継者とは先祖代々のお墓を引き継ぐ人のことで、お墓だけではなく、系譜(家系図)や祭具(仏壇や仏具、位牌、神棚など)を管理し、法要の主宰も行う。

甕棺墓
甕棺墓とは龜や壺を棺として埋葬する墓のことで、世界各地で見られるが、日本では縄文時代から弥生時代に、全国で発見されている。

ネアンデルタール人
ネアンデルタール人は世界最古の埋葬を行ったとされている化石人類です。

遺構
ここでの遺構とは、葬送に関わる遺構で、土坑墓、配石墓、古墳、火葬墓などのことを言います。

再葬墓
再葬墓とは遺体を土に埋めて骨の状態になったものを、壺や龜に入れ直して埋めた墓のことです。縄文時代や弥生時代に多く行われていました。

副葬品
副葬品とは葬儀に際して死者と共に埋葬される器物のことで、古くはネアンデルタール人の時代まで遡るとされています。

蔵骨器
蔵骨器とは、考古学で言う遺灰や遺骨を入れた容器のことで、現代では骨壷にあたります。

焼香
焼香とは葬儀で抹香を使って行う儀式のことで、原料は樒(シキミ)の葉や皮を粉末にしたお香です。焼香で焚かれる香りは仏の食べ物とされており、焼香する人の心と体の穢を取り除く意味合いもあります。

戒名
戒名とは、本来は仏門に入った弟子の証として与えられる名前のことですが、日本では故人に与えられる名前のことをいいます。宗派により法号や法名とも言います。

位牌
位牌とは死者の霊を祀るため戒名を記して仏壇に安置する木製の牌のこと。仏壇は故人がこの世に帰ってきたときの家だとすると位牌は故人の霊が宿る依代としての役割をしています。

永代使用料(非課税)
お墓を建てる時にお墓の区画(墓地)を永代で使用できる権利(永代使用権)の料金のことです。寺院によって永代使用料はそれぞれ異なります。

永代供養料(非課税)
永代供養料とは永代供養の料金のことで、一般的には33回忌までの各回忌の供養とその後の合葬の供養が含まれます。

堆肥葬
ワシントン州で2019年5月に合法化された新しい葬送方法。遺体を自然有機還元で堆肥にすることで自然の一部として循環でき、環境にもやさしく、土地不足の解消も期待される。現在他の州にも広がっています。

菩提寺
菩提寺の菩提はサンスクリット語ボーディーの音写で 死後の冥福 という意味です。死後の冥福を行う寺が菩提寺であり、家系(カケイ)として先祖代々のお墓があり葬儀や法事を依頼する寺、または檀家となった寺のことを指します。

お盆
お盆は元々「盂蘭盆会」といわれサンスクリット語のウランバーナの音写です。日本には7世紀頃に中国から伝わりその後日本独自の慣習として、祖先をお迎えし供養する行事となっています。地域によって7月や8月に行われます。


